タケダのグローバル化への挑戦

タケダのグローバル化への挑戦
2017年11月22日(水)に開催した「COMPANY Forum 2017」での武田薬品工業株式会社 相談役 長谷川閑史氏の講演内容をダイジェストでお届けします。
生物の進化の歴史で、生き残ったのは最も強い者や賢い者ではなく、最も変化に勤勉だったもの ― これこそ現世代の経営者が心に留めるべき言葉だという。 「じっと待って何もしないでいることが、結果として最大のリスクを負うことになる。トップが必死になってリードしない限り企業の大変革は実現しようがない」という長谷川氏が、変革をやり抜く勇気を語る。
生き残りをかけ、変化を捉えるリーダーの視点
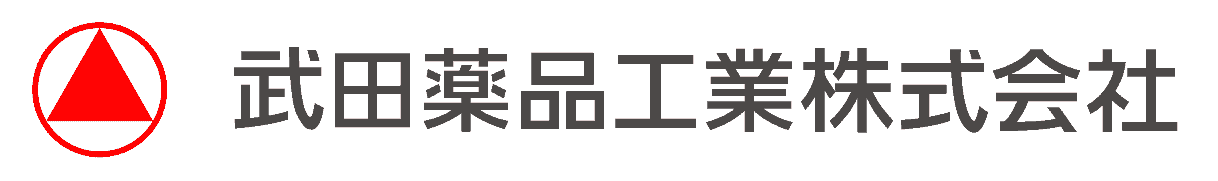
長谷川氏の改革の意図はどこにあるのか。まず、世界の医薬品市場に起こる2つのパラダイムシフトについて触れた。それは、新薬を創出するプラットフォームテクノロジーの変化と、製薬企業以外の台頭だ。わずか10年の間に、新薬は低分子医薬品からいわゆるバイオ医薬品と呼ばれる高分子医薬品へと移行。また、供給元として従来は製薬企業が70%以上を占有していたが、今やバイオテク企業やNPO法人、アカデミア等が50%以上を占めるようになった。
「タケダは低分子医薬品の開発でかなりの成功を収めた。しかし、その過去の栄光の上にあぐらをかいて新たなニーズに先駆的に取り組めていなかった。そのため、いかに革新的で差別化された製品を生んでいくかが最大の命題であった。また、医薬品市場の40%超を米一国が牛耳るという偏った競争下において、どのようにしてタケダの事業をグローバルに競争力のあるものへと変革するか。」それがタケダの社長として課せられた使命だったと長谷川氏は語る。
2003年の就任後、まず長谷川氏が行ったのは、研究開発や人材、ガバナンス等の主要9項目のベストプラクティスに対するベンチマーキングだ。その結果、大きく乖離する項目の一つに、売上に占める管理販売費があった。グローバルトップ10企業において、その割合はおおよそ8%であったのに対しタケダは12%。小規模な企業が業界首位に追随するために、効率性で負けていては手の施しようがないが、長谷川氏は「それすらも劣っているという、非常に悲惨な現実に直面した」と述べる。
そこで長谷川氏がとった戦略は、レッスンズ・ラーンドとして、グローバルスタンダードで成功体験を積んだタレントの登用だ。まさに米国が変革の中心に存在する理由の一つは、世界中から優秀なタレントを集めて強みを発揮させていくというエコシステムが形成されていることにある。2013年に新設したCFOポストにはフランス人を選抜した。その人選は、何も外国人に限ったわけではないが、日本人には適格者がいなかったという。かくして、新外国人CFOが変革の道半ば2年足らずで他社に引き抜かれていったことで、“ほらみろ、外国人を採るからだ”と相当な批判を受けた。「しかし、物事の一つひとつを実際に変えていくには経験のある人材にやらせるしかないという結論に至り、仕切り直して次のタレントを探し続けた」と振り返る。
批判を受けながらも、自ら考え、切り拓く
 武田薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社 相談役 長谷川閑史氏
さらに長谷川氏の前に立ちはだかったのは、パテントクリフ(大型医薬品の特許切れ)問題という壁だった。これは、タケダにとって年間3,000億円もの営業利益損失を招く事態である。この問題を克服するためにとった戦略は、研究開発力と販売力それぞれのギャップ・フィリングを目的としたM&Aだ。もちろん、自社内での研究開発を加速して領域を広げていくという手も考えられる。しかしながら、他製品よりも自製品をより良く捉えてしまうNIH(Not Invented Here)シンドロームに陥り、結局のところ実現した試しがなかったという。また、同族経営をしてきたタケダにとって、企業買収は初めてのこと。M&Aの実施においては、長谷川氏自らが指揮をとった。
また、癌領域に強みを持つバイオベンチャー、ミレニアム社を買収した時のこと。長谷川氏は「全く異なる領域の企業に対し、本社風を吹かせて無理やりマネジメントしたところで上手くいくはずがない」との熟慮の末、CEOの残留や社員へのリテンションボーナス付与といった様々な打ち手を講じた。時にそれは、“Paid too much retention bonus”と揶揄されることもあったが、「リテンションを維持しながらも最低の投資で済ませる、という見切りは経験を積んでみないとわからない」と語る。また、逆転の発想で、ミレニアム社のR&D部門のトップに本社の癌研究グループのマネジメントも任せた。
「約5年の間、彼らに自由度を与える一方で、彼らのやり方を勉強しノウハウを学んでいった。そうしてR&D部門トップを本社主導で登用して初めて、ミレニアム社をフルインテグレートできた。このようなステップを取らざるをえなかった。」
このように急速なグローバル化を推し進めた長谷川氏だが、「率直にいって、当時はこうした変化適応に備えて人材育成をする時間も、その能力もなかった」と回想する。それと同時に、グローバリゼーションは日本人の存在感を失くしていったと訴える。実際の現場では、多くの日本人社員から不満や不安の声が挙がった。「目の前にいるグローバルスタンダードのタレントを手本にして、自らを磨きたいと望むなら、どうぞ手を挙げてくれ。あなたの人材開発に投資をする用意はあるから、と。そうして納得してもらうしかなかった。」
事業領域の選択と集中を機に、海外赴任の希望を募った際には、100名超の日本人が手を挙げた。「こうした機会を通じて育った後に、転職してしまうこともあるだろう。ただ、それはそれで業界の発展に貢献してくれているのであれば嬉しいこと。日本人の性格としてリスクテイクを避けたがる傾向にあるが、イノベーションのハブに自ら飛び込んでいってほしい」とグローバルでの日本人材の活躍に期待を寄せた。
[講演紹介]
武田薬品工業株式会社 相談役 長谷川 閑史 氏
国内最大手の地位に甘んじることなく、ブレークスルーを起こしてイノベーションのパイオニアとして先陣を切るタケダ。長谷川氏は、2003年の代表取締役社長就任以降、同社の230年の歴史や経営の根幹となる価値観を尊重しつつ、自らが先頭に立ち、企業買収、事業のパラダイムシフト、外国人の登用など、タケダを事業のあらゆる面でグローバルに競争力のある会社にすべく変革を推し進めてきた。
長谷川氏が、経営の基本精神である「タケダイズム」を軸に力強いリーダーシップを発揮しながら、真のグローバル企業へと成長するための基盤をつくりあげてきた軌跡と、同社初の外国人社長クリストフ・ウェバー氏にバトンをつないだ今後のタケダの成長シナリオについて語る。
ワークスが主催する「COMPANY Forum」は、その年のトレンドに合わせた有識者や企業の方々に登壇していただくビジネスフォーラム。国を挙げて“働き方改革”が叫ばれた2017年は、Workforce Innovationをテーマにし、人工知能(AI)をはじめとする最先端技術・ビッグデータの活用等、多彩なセッションを開催しました。


.jpg)